 作品紹介
作品紹介

希望の鎖
伊藤 清
「この物質の謎を解かなくては」
少年の強迫観念に近い切迫感
それは父の遺志によるものだった――
東日本大震災の津波に流された父の遺品の顕微鏡が、5年後、アメリカの海岸で発見された。 海水に侵され続けたはずの顕微鏡は、真新しく、日々更新されているかのように機能が改変されていく。 この顕微鏡に偶然映り始めた物質の謎を解くうち、少年は命の起源ともいえる壮大な命題に立ち向かうことになる。
 プロフィール
プロフィール

伊藤 清
1952年6月1日 北海道生まれ。
獨協大学外国語学部英語学科卒業。
私立高校英語科非常勤講師を1年経験した後、都立高校英語科教員となる。
都立高校校長を最後に定年退職後、
私立高校2校で副校長を務め65歳で2度目の定年退職をした。
部活動では空手道部を指導し全国選抜大会に二度出場させた。
 インタビュー
インタビュー
『希望の鎖』が刊行されました。今のお気持ちはいかがでしょうか。
著者分として配布されたほとんどの部数を知人や友人、親戚などに配布しました。何人かから本気で感動したというお褒めの言葉をもらいますが、そんなときは刊行してよかったな、としみじみ思います。また、処女作ですので店頭に並ぶのを見るのは複雑な気持ちになります。嬉しいと同時に売れるかどうかが気になるのですね。もっとも売れるかどうかを気にしていたら、こんな本は書けませんが。
今回出版しようと思ったきっかけはなんだったのでしょうか?
教員生活を40数年やる中で、組織のリーダーが自らの考えや思いを発信することの大切さと効果を知りました。特に生活指導主任と校長を経験したときはその部門のリーダーとして発信することの効果がはっきりと感じられました。ところが定年退職を迎えてみると、発信したい思いや考えは膨らむばかりですが、発信する場面が無くなりました。市井の一人となった今、小説という形でならそれを表現して発信できるのではないか、と考えたのがきっかけです。
どんな方に読んでほしいですか?
「絶望」を「生きる力」に変えたい、という人にまず、お勧めします。この小説は読み手を架空の知的世界や心象風景に誘(いざな)います。そこから脱出(読み終えた)しときに、自分の心象風景が明るく変化していることに気が付いてほしいのです。
心の明るさや暗さには、そこに留まらなければならない明確な理由も根拠もない、と私は考えています。それらはつまるところ、自分で創り出すものだからです。
次に、現実社会を別な世界から見てみたい、という人にお勧めします。この小説は、荒唐無稽に変化する様々な場面に、ジェットコースターのように読者をダイナミックに運んでいきます。そのジェットコースターから降りたときに現実社会はどのように見えるでしょうか。その変化に、面白さを見出してほしいと思います。
 座右の一冊
座右の一冊
ツァラトゥストラ
著:ニーチェ
人生の大きな転換点

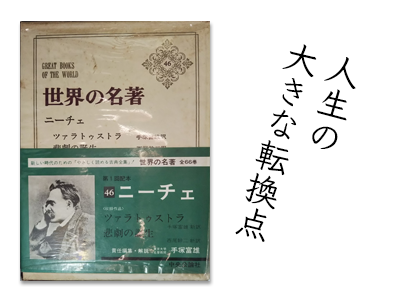
ここが魅力
この本との出会いは人生の大きな転換点となりました。私は、自分の人生について、前半の20年を「自己否定の20年」と位置付けています。次は「自己主張の20年」です。結局、どちらもうまくいかずに、新たな生き方を模索するようになりました。それが10年ほど続き、それを「迷いの10年」と位置付けています。これが終わるとようやく自分の生きる目標を見つけることができました。それは、変化です。自分の生きる目的を「自己変革」と定めました。よりよく変化するために生きるのです。そのために、私は自分の心に「自己変革エンジン」という強力なエンジンを搭載しました。
燃料は、身の回りに発生するドロドロとした不都合な現実です。この不都合な現実をろ過して燃やすのです。地面から湧き出る、ドロドロした原油を精製して、ハイクオリティーな燃料に転換するイメージです。このように、いつのまにか身に付けていた「自己否定」の生き方を変える転換点となったのがニーチェです。この一冊との出会いは撃的で、この場では表現できないほどの不思議な体験をしています。いずれ、ニーチェとの出会いも改めて整理してみたいと考えています。
 人生を変えた出会い
人生を変えた出会い
振り返ると、あのときあの先生に出会っていなければ、と思う先生が何人かいます。私が生まれた北海道の山村は開拓村の一つでした。父が4歳の時に北海道に渡ったと聞いています。父は明治42年に生まれているので大正の時代に入っていたのでしょう。初期の開拓団に遅れること数十年が過ぎており、豊かな入植地はなくなっていたようです。加えて、父はどういうわけか豊かさよりも苦労を意図的に選択するような生き方をしていました。
私が生まれたのは1952(昭和27)年です。サンフランシスコ平和条約によって日本は独立し、戦後の荒廃から復興へと本格的に舵を切ったころでした。小学校に入学してみるとほとんどの家庭には電気が付いていましたが、うちにはありませんでした。ガスや水道などいわゆる生活インフラというものは全くなかったものですから、生まれたときから毎日がサバイバルでした。電気を使えた里に住む子供たちとの格差を強く感じて育ちました。
学校に通うのも、険しいけもの道を6キロも歩くので大変でした。大雪や嵐、雨の日などはよく学校を休んだ記憶があります。いきおい、勉強は遅れていきます。そんななかで、私たち一家の事情を理解して粘り強く優しく勉強を教えてくれた先生が何人かいました。
母がしみじみ口にした言葉を今でもはっきりと覚えています。学校はありがたいな、と。それは、子供が学校に通うことによって勉強を理解し、成長していく姿を喜ばしく感じていたからです。その言葉を思い出すたびに、やはり、あのとき、あの先生に教わっていなければ、と思うのです。中でも、小学校3年生の時の担任(女性)と5、6年を担任(男性)してくださった先生の力がとても大きいと感じます。また、中学校に入学すると教師は教科ごとに異なりますが、当時、私が通った中学ではすべての教科を専門の先生で埋めることはできなかったようです。その中で、とりわけ熱心だったのが英語の先生でした。厳しい先生でしたが、とても分かりやすく、適切な課題を毎日出してくれました。私は、その課題をこなしているうちに英語だけは人並みにできるようになったようです。本来、語学は向いていないのですが、英語だけが人並みになったものだから、自分は英語ができると勘違いしたようです。それが、英語教師につながりました。勘違いが職業を決定づけたわけですが、勘違いしたおかげで職につけたとも言えます。
大学を卒業してからは、教師の道を一筋に歩いてきましたが模範教師とは相容れないタイプだった私に管理職を勧めた上司が一人だけいました。結局、この上司との出会いも運命的だったように思います。校長となって教職を退職することができました。やはり、人生の重要な節目は人との出会いと力によって導かれたような気がします。
 未来へのメッセージ
未来へのメッセージ
「生と死の接点」という考えを私はいつも持っています。生きることは死との接点上を周回しているように思うのです。さまよっているわけではありません。「死」という「ゼロの交点」を必死に周回しているのです。スピードが緩むと「ゼロの交点」に落ちていく。死に抗って周回するのが生なのかもしれません。
人間は生まれるには必ずしも理由は問われません。一方、死ぬには理由が要ります。理由なく死ぬことは日本では許されていません。どんな事故死でも原因・理由が付けられます。死亡診断書がそれになります。このように、死にはなんで死ぬかという原因・理由が明らかにされるのに対して、誕生はなぜ生まれるかという具体的、客観的な理由付けを求められることはないのです。
そこで誕生の意味づけは独自に求められることになります。望まれる誕生もあればそうでないこともある。意味ある誕生があれば意味を見いだせない誕生もある。「私はなぜ生まれてきたの?」という問いかけができるのが誕生なのです。それは死に求められる医学的な理由付けとは明らかに異なるものです。だからこそ、私は生きる意味は自分で創り出さなければならないと考えます。
昔のように世継・跡継ぎとしてあらかじめ決定づけられた生もあるだろうが、これからは、生の意味づけは自ら創出することが一層、求められるようになると思われます。自分でするわけだからどのような意味づけも可能になる。それは教育とも深く関係するでしょう。
人は現実から逃避すると生きづらくなる。非日常はルーチンな日常に彩を添える程度のものでなければならない。退屈な日常や苦しい日常を価値あるものとして豊かに輝かせるにはどうすればよいのか。それが、一人一人に求められる本当の生きる力であると私は考えます。それをはぐくむためには、日常の生活の中に夢を見られる想像力をもつことが有効なのではないか、と私は考えます。その夢の中に、生きる指針と希望とを見出すなら、ルーチンな日々を豊かに美しく、確かなものとして過ごせる、本物の生きる力になる、と私は考えています。
これから生きる若い人たちは、退屈さから逃れたいあまり突飛な行動に訴えたり、非日常の世界に頻繁に飛び込んだりすることは、実りある人生を困難にさせるだけでなく、生きる意味を一層、見出しづらくするように思います。真に生きる意味は日常の退屈さの中にあり、日々、新しく生成させるものだと私は考えているからです。


