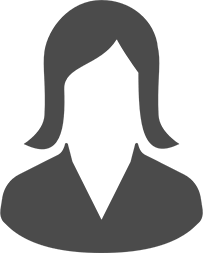妻のななえは、証券会社の洋一が来るといつも初めに日本茶を一杯だした。そして、すぐに退室していた。勇治からお茶のお代わり、と言われなければ、その部屋に顔を出す事は無かった。お代わりの時はほとんど無く、ななえはキッチンで煮ものなどを作って終わるまで静かにしているのだった。
ある日、勇治に緊急のオペの連絡が入った。通常、代理の人を、ひとり確保しているのだが、その人が体調を崩してオペに立ち会えなくなり勇治の携帯が鳴った。断わる訳にもいかず病院に向う事になったのだが、その日は洋一が来る日だった。ななえには洋一から資料だけを受け取る様に頼むと病院へと急いだ。
昼過ぎにいつもの様に洋一がやって来た。洋一は密かにななえを意識していたのである。洋一はまだ若いので随分と年上のななえを好きになるには、あまりにも不自然であるかも知れない。それも仕事でお客様の奥様となれば、実らぬ恋どころか成就するはずもなかった。勇治宅を訪問してななえの顔を見るのを、ことのほか楽しみにしている洋一だった。顔を見ただけで心臓が高鳴った。若い頃の恋愛とはまた違った大人の世界の女性のようで、洋一は一目惚れしてしまったのである。勇治宅に訪問するようになってから一年近く経っていたが、ずっとひとり胸の中におさめてきた。それが今日は主の勇治が不在である。話す機会などないだろう。洋一はすばやく名刺を取り出し自分の携帯番号を急いで書いてななえに突き出すように差し出した。ななえはその名刺をどうしようかと思いあぐねていると、
「受け取って下さい。連絡、待ってます」
と言い捨てるとドアをバタンと音をさせ庭の向こうに消えていった。雑だけど読みやすい字で書かれた番号をしばらく眺めていた。ななえはそれをクローゼットの隅に置いてあるポーチにしまった。そして、次の月まで出すことは無く、しまったままであった。
好きという対象でもなくただの外交員のひとりであった。
翌月、勇治のところへ普段と変わりなく洋一がやって来て、いつもと変わりなくななえはお茶をだし退室した。洋一はやり切れぬ思いでひと月を過ごしていた。もっと若くて可愛い人を見つけようと思うのだが、どうしてもななえの事が脳裏から一時も離れずにいた。月に一度の来訪の日が待ち遠しくて、こんなに苦しい思いははじめてだった。毎日、毎日、ななえの事を考えない日はなかった。
それは、ある日、突然やってきた。外回り中の洋一の前を、ななえが買い物帰りですれ違ったのである。洋一は思わず声をかけた。
「山本さん」
ななえはびっくりして驚いた。が、次第に小さな笑みを浮かべた。洋一はまだ、ななえの名前を知らない。
「こんにちは」
「こんにちは」
「お仕事ですか?大変ですね」
「いえいえ、山本様はお買い物ですか?」
「主人に頼まれた物を買いに出掛けて来ました」
洋一の頭はパニックになっていた。
「もし、もし良かったらコーヒーを飲みながら少しだけお喋り出来ますか?」
「う~ん、主人に𠮟られるわ」
「少しだけです。お願いです。本当にお願いします」
「どうしようかしら」
まだ五月だと言うのに洋一は顔中汗だらけにしていた。極度の緊張感がそうさせたらしい。洋一が、
「アイスコーヒー」
「私はカフェモカをお願いします」
とななえは言った。店員が去って行くと洋一はタオルで顔の汗をぬぐいながら、
「失礼をお詫びします」
「本当に失礼ですよ」
と言うとななえはケラケラ笑った。洋一は、
「まだ、お名前を知りません」
「あっ、そうだったわね。山本ななえと申します。ななえは平仮名です」
「そうですか、いい名前ですね。ぶしつけですが、ななえさんとお呼びしてもよろしいでしょうか?」
「はい。あなたは確か門倉洋一さんでしたよね?」
「えっ、覚えてくれていたのですね」
洋一は高鳴る胸の鼓動をななえに気づかれないかとドキドキしていた。
ずっと想いつづけていた女性が、ここに自分の目の前に座っている。夢ではないだろうかと思った。何を話していいのか頭の中は真っ白になっていた。注文した品を店員が運びに来て、ごゆっくりどうぞと告げると、洋一は喉がカラカラでアイスコーヒーのほとんどを一気に飲み干した。ななえはよく笑う女だった。何か嫌なことがあっても笑ってその場をしのいでしまう。家庭の中の些細ないざこざも、ななえの微笑みで随分と救われてきた。
洋一は名刺の裏に携帯番号をなぐり書きした事を詫びた。そして、つのる想いからずっと電話を待っていたと張り裂けそうな気持ちで言った。ななえは、
「もう私はおばさんよ。あなたにはもっとお似合いの方が見つかるわ。それに私には主人がいるのよ」
「それはわかっています。充分わかっています。けれど私の人生の中でただひとり一目惚れをしてしまったのです。許してください」
そして、
「たまに電話やメールをしたいのですが、いけませんか?」
「だめよ」
「もちろん、ご迷惑をお掛けしません。けれど、ご主人の山本さまにはご内密にして頂けないでしょうか?」
「それは出来ないわ。主人と相談させていただきます」
洋一は今にも泣き出しそうにななえを見た。それを見てななえは笑った。そして、
「わかりました。たまになら。これ、アドレスです。こちらから送ります」
先ほどの泣き出しそうな様から、何か勝ち誇ったように感じ飛びあがらんばかりである。まわりの客はみな二人を怪訝そうに見たのである。
それから三日後のよく晴れた日の午後、家事を済ませたななえはひとりアールグレイを淹れて飲んでいた。勇治は今夜は遅いと聞いている。子供たちは学校から直接、塾に行く日である。ななえはふと洋一の事を思いだした。ポーチから洋一の名刺を出して長い時間、眺めていた。随分と考えた。ななえは階段を一段、上がるような気持ちでメールを送った。
小一時間するかしないかの時間に洋一から返信が来た。そこには、ありがとうございますと、いう黒い無機質な文字があった。あの洋一とはかけ離れた冷たい文字に見えたのである。
それからは一週間に一度くらい洋一からメールが届いた。天気の事や、最近のニュース、など他愛もない内容だったが、ななえは簡単だが返信は必ずしていた。次第に、それが楽しみになっていくのがななえは少し怖かった。洋一とのメール交換のやり取りはもちろん勇治には言えないことである。
1ヵ月ほどそんなやり取りが続いていたが、ある日、洋一から、
「今度、お食事でもしませんか?」
と、メールが入った。ななえはどうしたものかと返信せずに考えているうち4、5日過ぎてしまい、そうこうしているうちに月に1回の商談の日を迎えてしまった。
洋一はなるべく平静をよそおい勇治宅をいつもの様に訪れたのである。そして、いつもの様にななえはお茶を出した。洋一は勇治の目線を確認しながら、ななえの目を見つめた。しかし、すぐにななえは退室してしまった。洋一は溢れる程の伝えたい言葉をのみ込み勇治との商談に入った。
その次の1週間は洋一からのメールが届かなかった。待っている訳ではないが有るものが無いと気になるのが女のずるさでもあった。
ななえは思い切ってメールを送った。
「お元気ですか?」と。
10分もたたないうちに洋一から返信があった。
「元気です」
「お茶ならいいですよ」
「本当ですか?後ほどご連絡いたします」
その日の夕方に洋一から
「明後日、ミルクという喫茶店。1駅先の桜台駅に午後2時、いかがでしょうか?」
「わかりました」
洋一は最後のわかりました、の文字を何度も確認して小躍りしたい気分であった。
洋一は約束の30分前にはミルクに来ていちばん奥の席に座った。二人でコーヒーを飲むのは二度目である。今回、食事は出来なかったが洋一は満足であった。ななえはちょうどの時間にミルクにやって来た。今日は薄い茜色のTシャツにGパンだった。
「お待たせしました」
「いえ、私も今、来たところです」
と洋一は言うと店員に、カフェモカ、二つと告げた。
「あら、覚えて下さっていたの」
「もちろんですよ。あ~でも、僕は何を話していいのかまったくわからなくなりました。緊張しています」
「おかしな方ね」
「そうでしょうか」
そう言うとまた汗をぬぐうのあった。
| ビオラの夜 【全5回】 | 公開日 |
|---|---|
| ビオラの夜(その1) 〜 道の駅 | 2020年11月30日 |
| ビオラの夜(その2) 〜 シティホテル | 2020年12月28日 |
| ビオラの夜(その3) 〜 あのひと | 2021年1月29日 |